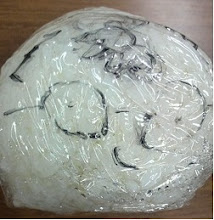3月11日の震災後、初めて東北に行きました。ずっと以前から行こうと思っていたのですが、なかなか実行に移す事ができませんでした。自分でも情けなく思っていました。しかしこのままでは今年に悔いを残すと思い、今年中に必ず行こうと決めました。ボランティアバスの存在を知り、地元のボランティア保険に加入し、戸田市HPでリンクされていた
「助けあいJAPAN」から見つけた
宮城県七ヶ浜町への
ボランティアツアーに参加しました。
恥ずかしい事に、実は参加前まで、七ヶ浜の事はほとんど知りませんでした。特に調べる事もなく、9日の23時に秋葉原駅前に集合しバスに乗り込みました。驚いたのは、意外にも若い女性の参加が多かったことでした。また僕より年輩と思える方々も多く参加されていました。次の日の作業があるので乗車後すぐに寝ました。隣に座った方に話しかけようかとも思ったのですが、何か迷惑にも思ったので話しする事もありませんでした。バスの中でツアー会社の方が「明日は天気も崩れることはなさそうです。」と仰った事にホッとしました。天候不良なら単なる観光になる、とも事前に聞いていたからでした。それだけは正直嫌でした。確かに観光も被災地への支援の力添えになるかとも思うのですが、僕の目的はあくまでボランティアだったので。
バスは現地のボランティアセンターが空く時間より遥かに早く七ヶ浜に到着し(朝7時位)、ボランティアセンターに行く前に
毘沙門堂へと向かいました。現地の方と思える(補助?)運転手の方が「ボランティア現地での写真撮影は禁止ですが、毘沙門堂から見える風景は撮影して構いませんので楽しんでください」と仰いました。その「ボランティア現地での写真撮影は禁止ですが」の意味がその時は正直ピンと来ませんでした。早く復興するようお参りし、そこから見える風景を撮影しました。
バスはボランティアセンターに向かいました。その車中、先程の運転手の方が淡々と語ります。
「七ヶ浜は入り組んだ湾の形をしており、その影響もあって津波の高さは15mから16mにもなるものでした。」
「海沿いの低い土地に立てた家は津波にほとんど流されてしまいました。高台にある家は津波の被害を受けず、はっきりと明暗を分けてしまいました。」
「震災が起きてから9ヶ月経ちますが、今だ手つかずの場所も残っています。」
そして僕の目の前に津波の被害を受けた町の様子が見えてきました。その時、先ほどの「現地での写真撮影は禁止」の意味がわかりました。東北に来る前に写真やテレビなどで被災の様子を見ていたのですが、実際に目の前にその光景が広がると、言葉が出てきませんでした。そしてボランティアを目的とした人間がこの風景を安易に撮影してはならないと痛感しました。
家の基礎しか残っていない土地、気が遠くなる程に集積場所に積み上げられた瓦礫の山、流された車や壊れた栽培ハウスなどがそのまま置かれている農地、津波で削られたと思える法面。
震災後、9ヶ月が経ちました。その間、現地の方々やボランティアの方々・自衛隊の方々などの努力によりここまでの瓦礫が撤去され、ヘドロなども取り除く事ができたのでしょう。しかしまだ手つかずの場所があるのです。それだけ震災の被害は凄まじいものだったのだと想像できます。現地の方々の悲しみも僕の想像を超えるものでしょう。
ただただバスの中から見える目の前の光景に唖然とするだけでした。
ボランティアセンターでは、その日に要望されているニーズをボランティア参加者の誰に振り分けるかの「マッチング」という作業が朝になされます。その日は全国から僕たちツアーメンバー30数名を含め、総勢350人以上の参加者が集結していました。その参加の多さも素晴らしいのですが、このメンバーと作業をマッチングさせるセンターのご苦労も大変なものと思います。
そして僕たちは今回「松林クリーン大作戦」と命名された海沿いの松林の瓦礫撤去作業を行いました。海沿いにも関わらず、引き潮で住宅地から流されたと思われる角材などの瓦礫を並行して走る道沿いに運び、集まった瓦礫をトラックの荷台に積み込む作業でした。
それを、午前10時30分から1時間。そして午後1時から45分。
するとボランティアセンターの方が「東京下町応援隊の方ですよね?別の事をしません?(笑)」と話しかけてきました。松の樹の根っこの掘り起こしでした。伐根というそうです。津波で折れてしまった松の樹の残った根をチェーンソーで切り取るのですが、その前に土で埋まっている根を掘り起こすのです。
これが大変な作業でした。悔しいけど全然掘り起こせません。殆ど掘り起こせないまま、作業時間終了の2時30分になってしまいました。
今回、ボランティアに参加して感じたことを書きます。
1.個人の力、というより僕の力の不甲斐なさ・無力さを痛感しました。
2.復興などと言う言葉以前の状況でした。まだまだその前にやるべきことは沢山残っています。
3.参加者誰一人、無駄な言葉を話す人はいませんでした。みんなが黙々と目の前の作業をこなしていました。
そして、最後に僕たちを担当してくれたリーダーの方の言葉が印象的でした。
「僕は東京から参加しているのですが、東京と被災地には大きな温度差がある事を感じます。」
この言葉の意味は大きいと思います。
ボランティア(というより人手)が絶対的に不足しているように感じました。しかしボランティアセンターのマッチングという作業を考えると、そうそう安易に増えてもうまく事が運ぶとも言い切れないようにも思います。難しい問題です。しかしはっきり言える事は、もう行政や政府の力量を超えた状況で、できるかぎりの応援しなければいけない現状なのです。
僕も初めての参加だったので大きなことは言えません。またボランティアに参加できなくても、また支援できなくても思いやる気持ちはきっとあると思います。しかし中には被災地の瓦礫を受け入れたくないという意見もあるそうです。放射能汚染があるないに関わらずです。僕はそういう人達に言いたい。「被災地に行って、想像を絶する量の瓦礫の山を見てから意見を言って欲しい」と。僕は福島の瓦礫だって全国各地で少しは受け入れるべきだと思います。この状況を一部地域に放置して良いのか?と訴えたい。
ボランティアセンターでは、バンダナとストラップ・そしてラーメンを購入しました。少しは支援の力になりたかったからです。また、ボランティアセンター横のNPOの建物にかかっていた寄せ書き入りのウィンドブレーカーが印象的でした。
また東北には行こうと思います。